

新たな社会教育・生涯学習研究の担い手に向けて、社会教育・生涯学習研究の魅力、意義、方法について語り、従来の研究の蓄積の上に、新たな社会教育・生涯学習研究を展望していく。
学生など研究者だけでなく、自分たちの実践を意識化しさらに高めようと社会教育・生涯学習研究を志す、層の幅広い人たちにも最適。自らの立場性や前提条件と社会教育・生涯学習研究との関係について、整理できるよう配慮。
変化の波にさらされる時代における、社会教育・生涯学習研究には、歴史を通して蓄積されてきた知を現代に生かす責務と同時に、新たな時代にふさわしい学問の構築をめざす責務がある、本書ではそれらを明らかにしていく。
<執筆者>
津田英二、梨本雄太郎、久井英輔、松橋義樹、永井健夫、岩崎久美子、松岡廣路、小林卓、守井典子、青山鉄兵、冨永貴公、伊藤真木子、鈴木眞理
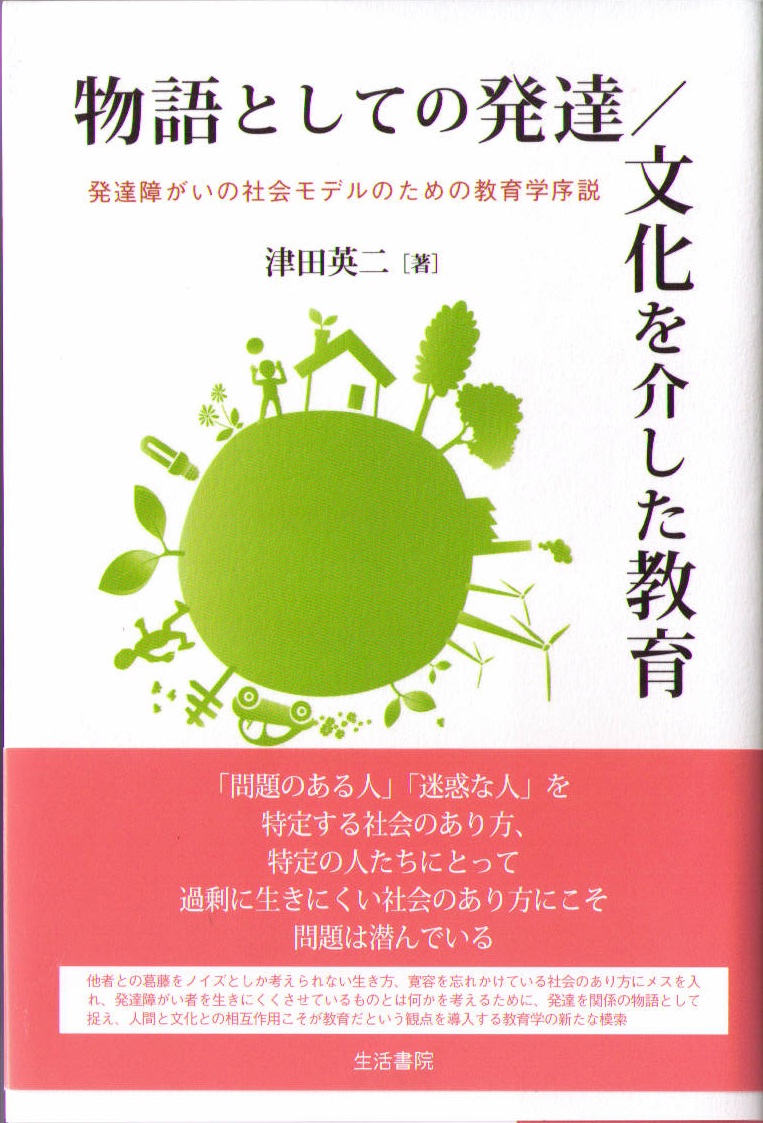
【本文からの抜粋】
はじめに
2011年3月に起こった東日本大震災は、日本を揺るがし、世界を揺るがした。それから1年余りが経った今、あの震災によって、私たちは何を経験し、何を学び、何を変えてきたのかということを振り返る。すると、あの衝撃の大きさに比べて、その後の日本社会全体の変化はあまりに小さいように感じられる。あの原発でさえ、自粛ムードの後は再稼働に向けて着々と準備が進められているような気配である。
2012年6月、障害者自立支援法に代わる新法(障害者総合支援法)が成立した。たくさんの障がい者を巻き込んだ議論の末、出てきたものは障害者自立支援法の延長でしかないようなものであった。変化は混乱をもたらすからというのが、厚生労働省の説明だった。変化をもたらそうとした民主党の勇み足だったとも言われた。民主主義を徹底することは勇み足なのか。変化をもたらそうとして議論に加わった人たちは、当然のことながら怒りの声をあげている。
私たちの社会は、ちょっとやそっとのことでは変化しないようにできあがってしまっているようだ。人間の意志がシステムを動かしているのではなく、システムが人間を操作しているという事実が、来る日も来る日も眼前に突きつけられるような気がする。イリイチが1970年代に「制度の過剰が臨界点に達している」と警告して40年以上が経ち、再びイリイチの言葉の意味を噛み締めている。
このままではいけないという不安は、時代の空気にさえなっている。行動を起こさないといけないと誰もが思うようになってきている。しかし、どうやら多くの人たちは「強いリーダーシップ」を待望しているようだ。優れたリーダーが、古い制度を刷新し、時代を変えてくれることを願っているように感じられる。私には、そうした動きにも危うさが感じられる。強いリーダーは、新しい強力な制度によって人間を支配しようとするからである。不安定な時代に、強い支配を受けることによって不安を解消しようとする人間の心理を描いたフロムの『自由からの逃走』(日高六郎訳、東京創元社、1965年)を思い出す。
私たちは、私たちの足元から、身体を伴い経験に基づいて、変化をつくっていかなければならない。本書を世に問う最大の動機がここにある。
(中略)
さて、こうしたことを考える伏線に、本書では発達障がいの問題を介在させた。初発の単純な問題意識として、働きかけの過剰を当然のこととする社会が、発達障がいの問題を形作っているのではないかという疑問があった。
私たちの社会の中で、特に学校教育において、発達障がい者は問題のある人として扱われる。逆に問題のある人に発達障がいのレッテルを貼ってきたというほうが適当かもしれない。社会は、発達障がい者が問題のある人ではないことを自ら証明してみるように迫る。早期発見・早期対応によって、社会に適応させることを至上命題にする。早期発見・早期対応の現場で働いている人たちは、実際に苦しんでいる発達障がい者の助けになろうとしている。実際にそれによって生活の質を向上させる人もいるのだから、そうした実際の実践は肯定的に評価されるべきだと思う。
しかし、早期発見・早期対応で問題解決を図ろうとする社会のあり方には問題を感じざるをえない。根源的な問題は、問題のある人、迷惑な人を特定する社会のあり方、またそうした人たちにレッテルを貼ろうとする社会のあり方にこそあるのではないだろうか。特定の人たちにとって過剰に生きにくい社会のあり方こそに問題があるのではないか。他者との葛藤をノイズとしか考えることができない私たちの生き方、寛容であることを忘れかけている社会のあり方に、何とかメスを入れることはできないか。発達障がいの問題とは、社会全体の問題を、発達障がい者の個人の問題として押しつけることで現象しているのではないか。
私たちは、発達障がい者を何とかしなければならないと考える前に、あるいは少なくともそれと同時に、発達障がい者を生きにくくさせている社会のあり方、私たちの生き方を考え直さなければならないのだと思う。
私たちの社会には、たくさんの問題が溢れている。それらの問題を解決しようとすると、私たちの生活や生き方の変化が要求される。そうした変化は私たちの多くにとって葛藤を生じさせる。問題と私たちとの間の葛藤でもあるし、私たちの内的な葛藤でもある。しかし、その葛藤と向き合わなければ、私たちは問題を私たちの生と切り離すか、強いリーダーに問題解決を委ねるしかない。私たち個々人が葛藤と向き合うことこそが、今の時代に求められているのではないか。教育は、葛藤と向き合うことを促すところに大きな役割があるといえるのではないか。
以上、少しは読者の指針になるのではないかと思い、荒削りな本書の内容を、さらに荒削りにして述べてみた。
(以下、略)
【本文からの抜粋】
はじめに
ある集会で話を頼まれて出かけたとき、障害についての話をひととおり終わってから、ひとりの女性が「かわいそうな障害者のために、私はずっとボランティアをやってきたのです」といった内容の発言をした。障害のある人たちを「かわいそうな人たち」と一括りにするのは一方的な見方だという話をさんざんした後だったので、私はその発言にどう返答したものか、とても戸惑いを覚えた。
しかし、「不幸」とか「かわいそう」といった観念を一般化してしまう傾向から逃れることは、私にもできているわけではない。
つい先日、ハンセン氏病の療養所に行き、ひとりの年配の男性のライフストーリーをじっくりと聞く機会があった。若かりし日に、愛する家族と引き離されて療養所に強制収容させられ、身体が徐々に動かなくなっていく中で死ぬことばかりを考える日もあったといった内容であった。
私にとって貴重な体験だったのは、彼の波瀾万丈の人生に感情移入して聞くことができたことでもあったが、それよりもむしろ、社会的に構築された深刻なストーリーと、生で聞くどちらかというと明るいトーンでの話との間のギャップに驚いたことであった。話された経験はいちいち重たい内容であり、彼の歩んできた道の険しさ辛さは想像を絶していた。しかし、目の前にいる彼は、その過酷な運命の中でいきいきと生きてきたことを語っていた。辛い経験をしたからといって彼の人生が不幸だとか無意味だとか考えるのは誤りであり、彼に対して失礼なことなのだと、率直に思った。
本書を書くまでに、多くの知的障害のある人たちと関わってきた。彼らや彼らの家族の多くは、いじめや排除など、社会の中で辛い目に遭っていた。溢れる欲求を抑えきれず、しかし障害があるからという理由で欲求を満たすことが困難な人がいて、いつもトラブルを起こしていた。自傷行為で身体中が常に傷だらけの人もいた。不眠症で障害のあるわが子に付き添って、30年も慢性的に寝不足の母親もいた。ちょうど子育て期にあって、子どもの夜泣きや夜尿で起こされるだけで不機嫌になってしまう私を恥ずかしく思うこともあった。
とはいえ、彼らから悲壮感を感じたことは稀であった。いつも和やかな笑顔に包まれていることが多かったし、そうでなくてもユーモラスな身体の動きや発言で周囲を和ませてくれるような人も多かった。たいへんな思いをして介助に努めている母親は、日々の過酷な経験をおもしろおかしく語ってくれることもあった。
どの人も自分の人生をいきいきと生きようとしている。どの人の人生も、障害があるからという理由だけで無意味などということは決してない。この本では、まずそのことを語りたいという思いがある。
しかし、その一方で、あらゆる関係が絶たれて孤独になるということは怖ろしいと思う。医師である額田勲が書いた『孤独死』(岩波書店、1999年)は、阪神淡路大震災の復興期に、仮設住宅や復興住宅で、社会関係を絶たれた人たちが「孤独死」していく状況をリアルに描いた本である。人間は、関係の中でいきいきと生きようとする気力を保つものなのだということを教えてくれる。
現代社会では誰でもが孤独に陥る傷つきやすさをもっているが、障害をもっていること、障害のある人が家族にいることは、その傷つきやすさを増幅する働きをもちえる。施設への入所や母子の共依存は、その典型的な例だろう。母親が、障害のある子どもを殺したり、子どもと心中を図ったりする例が、年に必ず数件はある。
障害のある人やその家族の社会関係を永続させること、あわよくば豊かにしていくことが、知的障害のある人たちとの関わりの中で、何よりも重視すべきことなのだ。そのことよりも大切な視点はないと思う。その上でさらに関係の質も問わなければならない。お互いにとって心地よい関係はどのようにして可能であるのか。
知的障害のある人たちとの関わりの中で人間存在について考えを深めることが、本書の根源的なねらいである。まだまだ未熟であることは隠しようがないが、本書はその中間報告だと思っていただけたらと思う。
since March 2005